体験場所:三重県I市の某小学校
これは私の小学校での話です。
私の通っていた三重県I市の小学校のグラウンドには、ド真ん中に大きな楠木が立っています。

学校ではこの木をスクスク育つ元気な子供の象徴として扱っていましたが、如何せん立っている場所があまりにも厄介です。なにしろグラウンドのド真ん中ですから、サッカーや野球をするにしても邪魔にしかなりません。
なぜそんな場所に巨木が立っているのかと言うと、実はこの小学校がある地域一帯は、元々は古い神社に属する神様の森が広がっていた場所なのだそうです。
その森が開発され、今ではすっかり普通の住宅街になっていますが、地域の所々には今も御神木とされる大きな古木が点在していて、それぞれ注連縄が張られています。
小学校のグラウンドのド真ん中にそびえる楠木も、見た目は普通の木ですが、その御神木として扱われていたようなのです。
そんな楠木ですが、私が小学校にいた頃には3本立っていました。

1本でもたいがい邪魔なのですが、それが3本ともなるとかなり不便です。それでもご神木ですから無下にできず、この楠木は長い間、グラウンドのド真ん中にそびえ立っていたのです。
それを他所から赴任してきた教頭先生が、邪魔だから伐採してしまおうと主張し、私が小学生の頃に実際に伐採されることになったんです。
夏休み中に3本とも伐採されることになり、初日に1本が伐られて片付けられたのですが、その日の帰り、伐採業者が怪我人を出す事故を起こしてしまい、工事は一時中断。

それでも夏休み中に業者を変更し、続いて2本目が伐られました。その時は無事に完了しました。
業者変更などによる日程調整でスケジュールが遅れたこともあり、夏休み中の伐採は2本で終わり、残り1本は冬休みに伐られることになりました。
前置きが長くなってしまいましたが、本題はここからとなります。
2本目の伐採から二か月ほど経った秋頃、私たちの学年は臨海学校で伊勢志摩の方へ行きました。
季節は秋ですので別に泳ぐわけでもなく、水辺で遊んだりするようなキャンプみたいなものです。
団長として先ほどの教頭先生も同行しました。
現地に到着し、各種行事を済ませ、夕方になる頃には夜のキャンプファイヤーの準備をすることになりました。
私の所属する班は薪の用意を担当していたのですが、どうも手違いがあったようで、キャンプファイヤー直前になって追加の薪を取りに行くように教頭先生から指示を受けました。
薪が置いてある場所はキャンプファイヤーの会場から少し離れた林の中の広場です。
あたりは既に薄暗くなっており、鬱蒼とした林の中は小学生時分の私には不気味に感じたのですが、担任の先生が同行してくれますし、言っても施設の敷地内ですので、特に危険があるような場所ではありません。
思った通り、林の中を5分ほど歩くと、あっけなく薪が置いてある広場に着きました。
するとそこに、一人の男性が立っていました。
それは、先ほど私たちに薪を取ってくるように指示した教頭先生でした。

しかし、先ほどまでの教頭先生とはどことなく雰囲気が違います。
辺りが薄暗いせいかもしれませんが、顔色は悪く、どことなく生気が無いように感じます。
怪訝に思った担任の先生が声をかけようと近づきますが、教頭先生はそれを無視して更に林の奥へと入って行き、そのまま見失ってしまいました。
私たちは不思議に思いつつも、各自薪を持ちキャンプファイヤーの会場に戻ると、そこで教頭先生が設営の監督をしていたのです。
特に不自然な様子もなく、他の先生や生徒と会話をしながらキビキビと設営の為の指揮を執っており、顔色も至って健康的です。
担任の先生が声を掛け、「さっきは何をしていたんですか?」と質問をしますが、教頭先生は怪訝な顔をして、自分はずっとこの場所にいたと言うのです。
会場に残った先生や生徒も教頭先生はずっとこの場所にいたと言うので、さっきのは何かの見間違えなのだろうということになり、その日は何事もなくキャンプファイヤーが行われ、臨海学校も無事に終了しました。
それから二週間ほど後、教頭先生は出張先で急死しました。

死因は病気ということだったのですが、特に持病のようなものは無かったそうです。
人は、自分のドッペルゲンガーに会うと死期が近いという話があります。
もしかしたら、私たちが見たのは教頭先生のドッペルゲンガーだったのかもしれません。
そして、そのドッペルゲンガーを見せたのは、今も学校の校庭に一本そびえ立つ最後の楠木だったのでは…?
でもそうだとして、なぜそれを教頭本人ではなく、私たちに見せたのかは謎なんですが…
『御神木の祟り』
学校ではしばらくそんな話が噂されていました。

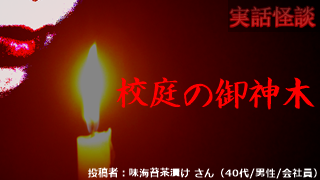
コメント